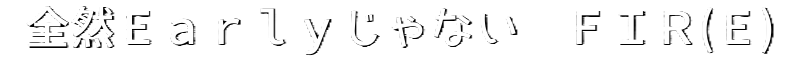新NISAとiDeCoとでどちらがいいか?という話を聞くことがあります。
もちろん、人によって違う、というのはあるでしょうけれど、この両者は、
・新NISAは完全非課税
・iDeCoは課税の先送り
である、という基本事項は把握されておいた方がよいかと思います。
iDeCoは課税の先送り
私も最初iDeCoを始めたきっかけは、「掛金”全額”が所得控除になる」ということでした。私の場合の掛け金は上限月1万2千円でしたので、年額で14万4千円。
これに、所得税率20%、住民税率10%、計30%を掛ければ、年末調整で約3万円弱返ってきて、翌年度は住民税が約1万円強減額され、合計で年間約4万円強の税金が返ってくる/払わなくて済む、と思うと、「これはいい小遣いだ。やらなきゃ損」とほくそ笑んでいました。
その時は、「受給時には受給額全額に税金が掛かる」なんてことは夢にも思わずに。
例えば、生命保険などの保険であれば、給付時に税金が掛かるにしても、自分が掛けた掛金は(いわば経費として)差っ引いた上での話です。
ところが、iDeCoは、自分が掛けた掛金も含めて受給時に税金が掛かります。最初は、「えっ、なんで?」と理解できませんでした。
でも、iDeCoは“自分で掛ける年金”だと考えると全く不思議ではありません。
iDeCoは“自分で掛ける年金”
iDecoは、厚生労働省所管だけあって、基本的に「年金」と同じ”仕組み”です。
今だって、会社員が毎月給料から天引きされている厚生年金の掛け金は、「社会保険料控除」として、全額所得控除された上で、年金受給時に、(掛金も含めた)年金受給額に対して税金が掛かります。(当然基礎控除等の控除はありますが)
要は、「掛け金には税金はかからないが、掛け金を含めて受給時に税金が掛かる」という仕組みは、年金もiDeCoも基本的には同じです。
つまり、年金もiDeCoも、「働いている時のおそらく10~20%程度の所得税率の時には税金を払わずに、年をとって年金をもらうようになった時に、(おそらく)5%の低所得税率の時に税金を払う」という仕組みです。
いわば、その税率の「差」がお得になります。(年金として分割受給するときの話として)
(正確に言うと、iDeCoの運用は非課税で運用できる、という点もお得と言えばお得なのですが)
また厳密にいえば、iDeCoを掛けている時と、受給するようになった時とではおそらく数十年の時間差があり、「お金の価値は徐々に減っていく」ということまで考えると、上述の所得税率の差はどこまでお得か?という話にもなりますが、そこまで悩むとキリがないので、まずは、「若い時と年をとった時の税率の差がお得」という理解をしておけばいいのではないかと思います。
(なお、iDeCoの場合は毎月事務手数料も掛かりますが、証券会社にもよるかもしれませんが僅かなので、誤差の範囲としてここでは無視します。)
結局、iDecoと新NISA、どっちがいい?
「20代ですが、iDecoと新NISAどっちがいいですか?」みたいな話を聞きます。
この答えは明確だと思っています。
課税所得(収入ではない!)が195万円未満だと所得税率5%であり、人によって当然異なりますが20代ぐらいの所得税率は5%の可能性は十分あるかと思います。
(所得控除や世帯構成などが人によって違うため一概には言えませんが、仮に社会保険料控除だけを考えても、課税所得195万円の独身会社員は、400万円強以上の年収があるかと思います。)
一方、年金収入者の所得税率は5%の方が多いかと思うので、であれば、先ほど述べた「iDecoは税金の先送り」ということを考えると、他に新NISAという非課税制度がある以上、“20代のiDeCoはほぼほぼ意味がない”ということになるかと思っています。
(65歳以上の年金収入は特に所得控除が大きいので、これも人によって当然異なりますが、65歳以上なら年300万円(月25万円)ぐらいでも所得税率5%になるかと思います。)
なので、非課税制度のお得な使い方という意味では、「iDecoと新NISA、どっちがいい?」に対する私としての答えは、
「新NISA枠1,800万円分が全部埋まったら、iDeCoを始める」
でいいと思っています。(iDeCoを始めるころには、自身の所得税率もそれなりに上がっているかと思います。)
なお、以上はiDeCoを年金として受給する時の話ですが、一括受給した時の退職控除に関しては、また別の機会に述べたいと思います。